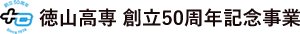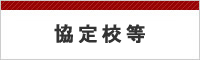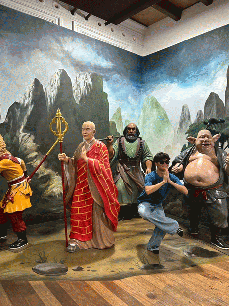私はPASMYのPM部門で、企業運営の仕組みについて学びました。PMとはプログラムマネジメントを指し、社内外の調整や顧客との協議を通じて、生産活動全体を円滑に進める役割を担っています。そこでは5人のマレー系スタッフが所属しており、5日間にわたり温かく迎えていただきました。
初日は工場全体を見学し、生産活動の流れをおおまかに学びました。品質を守るための細かな工夫が随所に見られ、特に印象に残ったのは、製品の自重を利用して動く運搬機や、極小の部品に至るまでQRコードを付与し在庫や品質を徹底的に管理する仕組みでした。こうした仕組みに触れることで、効率化と生産の確実性を両立させるものづくりの工夫を実感しました。
また、日本人スタッフから概要を教えていただいた後も、現地の方々が丁寧に生産ラインを説明してくださり、理解をより一層深めることができました。
二日目以降はPMの具体的な業務について学びました。グループ内の生産部門の方や日本人のスタッフを交えたオンライン会議にも参加させていただきました。特に印象的だったのが、同じ部署の方が英語、日本語、マレー語を瞬時に切り替えながら積極的に発言しており、世界に通用する言語能力及びコミュニケーション能力はとても強いものだと感じました。社員間でフレンドリーに、時には談笑も挟みながら朗らかな雰囲気で仕事をこなす様子は円滑な連携を実現できている理由のように感じました。
また、同じ部署内の方の退職祝いにも参加し、ショートケーキとカフェオレをご馳走になりました。部門長も今月で転職されるとのことで、「同じ職場で勤め上げることが必ずしも当たり前ではない」という働き方の価値観の違いを強く感じました。
加えて、中国のお盆にあたる伝統行事にも参加しました。線香を額に三度掲げて祈りを捧げ、紙のお金を燃やして金運を願い、その後は中国料理のご馳走をいただきました。普段親しんでいたマレーシアの味わいとは異なり、独自の風味ながらとても美味しく、食文化の多様性を肌で感じました。芋あんを弾力の強い黄色いお餅でくるんだものが特に美味しく、優しい味わいで何個でも食べられる勢いでした。
今回参加させていただいたのは中国の行事のみでしたが、異なる文化や宗教が同じ職場で自然に共存している姿に触れることができました。イスラム教の方が礼拝を行い、中国系の方が伝統行事を守る、そうした多様性の調和こそが、この職場の大きな魅力であると強く印象に残りました。 (情報電子工学科4年 熊本航大)